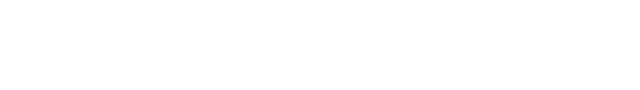ダニ媒介性脳炎
ダニ媒介性脳炎とは
ダニ媒介性脳炎は、ダニ媒介性脳炎ウイルスを保有しているマダニに咬まれることで感染する疾患です。ダニ媒介性脳炎ウイルスは、「フラビウイルス科フラビウイルス属」に分類されるウイルスで、多くの地域で存在が確認されています。主な感染経路はマダニに咬まれることですが、ダニ媒介性脳炎ウイルスに感染したヤギの生乳を飲む事でも感染する可能性があります。ダニ媒介性脳炎ウイルスを保有するマダニがいる地域でのレクリエーション等を行う場合にはマダニに咬まれないように十分注意することが必要です。
症状
日本で多い極東亜型のダニ媒介性脳炎ウイルスに感染すると筒右や発熱、悪心・嘔吐などの症状が現れます。さらに悪化すると、精神錯乱、昏睡、痙攣、麻痺などの脳炎症状が出現することがあり、記憶力低下、気分変調、集中力低下、運動失調症などの後遺症が残る人もいることが報告されています。
発生状況
ダニ媒介性脳炎が報告されている匡は少なくとも37カ国以上に上り、全世界で毎年およそ10,000~15,000例の感染例があると予測されています。しかし、ダニ媒介性脳炎の検査の実施状況は国や地域によって違うため、患者数は少なく見積もられている可能性があると指摘されています。
国内では、2024年8月までに北海道で7例のダニ媒介性脳炎症例が報告されています。2018年までは5例の報告がありましたが、2024年には新たに2例の発症が確認されました。北海道では、抗ダニ媒介性脳炎ウイルス抗体を保有する動物がさまざまな地域に生息していることが明らかになっているため、特に感染に注意が必要な地域と言えるでしょう。しかし、北海道以外でも抗ダニ媒介性脳炎ウイルス抗体保有動物の存在は確認されているため、感染リスクのある地域が北海道だけではないことを知っておくことも重要です。
また、マダニの活動は3月から11月にかけて活発になります。ダニ媒介性脳炎の発症は、マダニの活動が活発になるじきに増加するため、この時期においてはマダニに咬まれることがないように気をつける必要があります。
感染経路
マダニは、卵から孵化したのち、幼ダニ→若ダニ→成ダニという段階を経て成長していきます。このうち、ダニ媒介性脳炎ウイルスを媒介するのは主に若ダニと成ダニであることが知られています。
通常では地面から1.5mあたりまでの範囲に生息していて、動物などの血を吸うために移動します。マダニは宿主動物に寄生したあと、数時間経過した頃に血液を吸い始めます。ダニ媒介性脳炎ウイルスは、吸血直後にダニの唾液を介してダニから宿主動物に感染します。
予防策
野外では長袖長ズボンの着用、首にタオルを巻く、裾や袖の隙間をなくすなどで肌の露出を防ぐ。
野外から戻ったら上着や作業着は家の中に持ち込まず、シャワーや入浴でマダニの付着がないかを確認する。また、マダニが付着していた場合には、ガムテープを使って衣服に付着したダニを除去する。
ダニ媒介精嚢炎予防の為のワクチン接種を受ける。
治療法
ダニ媒介性脳炎に対する抗ウイルス治療がないため、対症療法が中心となります。髄膜炎や脳炎、髄膜脳炎を起こしている場合は入院が必要で、症状の重要度に応じて治療が行われます。そのため、防護服の着用や忌避剤の塗布、ワクチン接種などの予防策が非常に重要となっています。